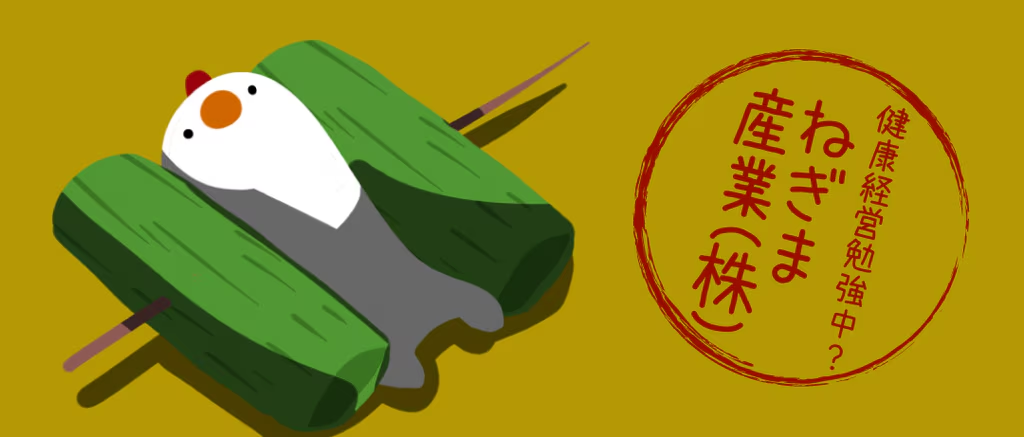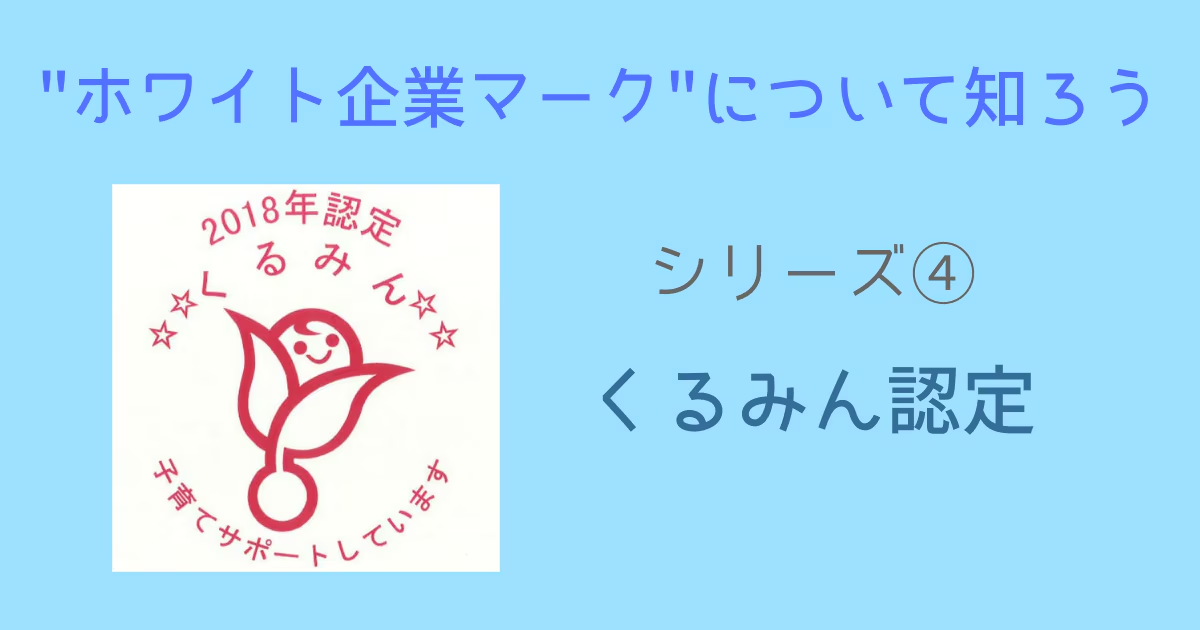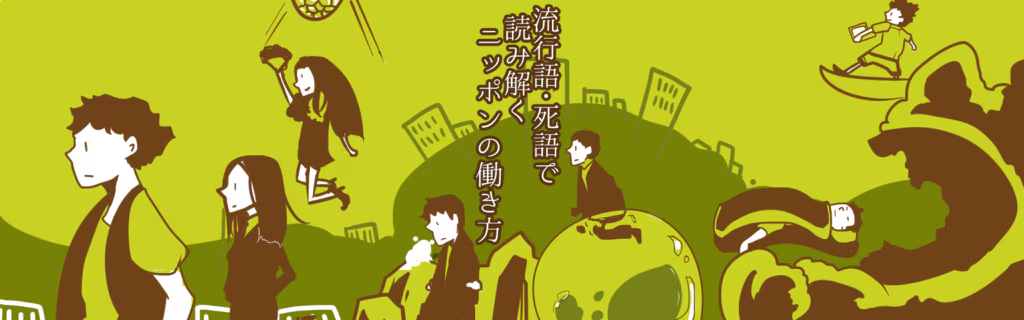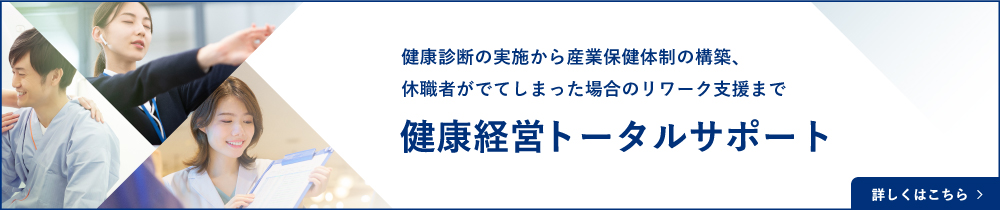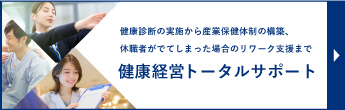〈判例から読む〉有給休暇を”時季変更”するときの注意点と対応のポイント
(更新:)


10月は「年次有給休暇取得推進期間(厚生労働省発案)」です。
4月に新しく入社した従業員にも有給休暇が付与され、これから有給休暇の取得シーズンがやってきますが、事業の都合によっては従業員の希望する日に有給休暇を取らせることが難しい場合があり、やむなく取得日を変更することもあるかと思います。しかし、安易な有給休暇の時季変更は、訴訟などのトラブルの原因にもなるため注意が必要です(※)。
時季変更権の注意点を過去の裁判例からみていきましょう。
※時季変更権行使のポイントについては過去の記事「繁忙期に従業員から有給休暇申請が!取得日は変更できる?時季変更権を解説」にて紹介しています。
目次 [非表示]
長期間連続する有給休暇の取得申請があったら?
従業員から1か月連続する有給休暇申請が…
時事通信社事件(最二小判平12.2.18)の判例を見てみましょう。
この事件では、従業員から約1か月の連続した年次有給休暇の申請がありました。
会社は「1か月も休まれたのでは業務の運営に支障が出る」と判断。また、代わりに勤務できる人員が確保できないという理由から「1か月の休暇を2分割し、2週間ずつの休みにしてほしい」と、従業員に時季変更の要望を伝えました。
しかし、従業員はそれに従わず無断で欠勤したため、会社は業務命令に違反したという理由で、ボーナスを減額して支給するなどの処分を行いました。
従業員はこの時季変更と処分に不服を申し立て、処分の無効と減額分の賞与を支払うことを求めて提訴しました。
企業の時季変更と処分は有効と認められた
この時事通信社事件では企業側が勝訴しています。
通常であれば、企業には従業員が有給休暇を取得できるよう、人員不足などをカバーすることが求められています。
しかし、時事通信社事件の判例では、従業員が連続した長期間の有給休暇を取得することで正常な事業運営に支障が出る可能性が高いことや、休暇が長期になればなるほど企業には人員の確保は難しくなることが予想されると最高裁判所は判断しました。
こういったケースであれば、企業の時季変更権行使は有効であることが判例から読み取れます。
いずれにせよ、従業員の休暇期間が長期化する場合などには、事前に企業と従業員との間で十分な調整をすることが求められます。
有給休暇の直前になって時季変更しなければならない状況なったら?

あらかじめ決めていたスケジュールで有給休暇が取れなくなったケース
高知郵便局事件(最二小判昭58.9.30)を見てみましょう。
高知郵便局は年度の初めに、有給休暇の希望日を職員にあらかじめ提出させ、所属長が業務の繁閑を予想した上で有給休暇を取得させる形態をとっていました。
しかし、選挙関連の郵便物が発生したことにより業務量が増え、所属長は当初予定していた有給休暇の付与日2日前に時季変更の通知をしました。
職員はこの通知を無視して欠勤したところ、戒告処分となってしまいました。職員は戒告処分の無効を主張し、提訴しました。
有給休暇取得日“直前の時季変更”がトラブルを生む
判決は職員側の勝訴でした。
理由としては、有給休暇取得日の“直前になって”時季変更がなされたことが挙げられています。
高知郵便局事件の場合、有給休暇の取得スケジュールは年度の初めにあらかじめ決められており、その時点で有給休暇の取得が成立していました。
労働基準法第39条では「事業の正常な運営を妨げる場合」ならば時季変更が可能と定められていますので、一見このケースであれば当てはまりそうです。
しかし、選挙による郵便物の増加は「予測可能な事態」であると判断できるため、使用者側は忙しくなることが判明した後、速やかに有給休暇取得日の調整を行うべきでした。
また、もしこれが従業員の保有する有給休暇の“消滅期限”直前であったならば、時季変更自体が禁止されていますので、使用者はなす術がなくなってしまいます。
このように、すでに取得時季が決まっている有給休暇を変更する場合には注意が必要ですが、適法に運用すれば、有給休暇の計画的付与はトラブルの回避にも効果的です。
特にトラブルになりがちな有給休暇の“消滅”対策にも役立ちます。
有給休暇関連のトラブルを回避するのに効果的な方法

トラブルになりがちな有給休暇の“消滅”期限
有給休暇は付与された日から起算して2年後に消滅してしまいます。そして、この消滅直前の時季変更権行使は労働基準法で禁止されています。
一方で、2019年4月の労働基準法の改正により、有給休暇を取得させていない企業には罰則が課されるようになりましたので、従業員には有給休暇を取得させなければなりません。
“休みたがらない従業員”が多い企業にとっては悩みどころでしょうし、休まない従業員たちの入社が同時期であれば、有給休暇の消滅サイクルも同時にやってきてしまいます……。
有給休暇を従業員からの申請にのみ任せている場合には、取得方法を見直しすることも検討すべきでしょう。
有給休暇の“取得計画”を立てる
有給休暇を計画的に取得させる方法は一つの解決策になります。
手順としては、まず従業員それぞれの持っている有給休暇の日数をカウントし、事業の繁閑や従業員との話し合いの上、有給休暇取得日を先に決めてしまいます。
例として、厚生労働省が「仕事休もっ化計画」として推奨している有給休暇取計画の例を以下で紹介します。
①一斉付与方式:「○月○日に全員で有給休暇を取りましょう」とアナウンスし、操業を止めるなどして全従業員を一斉に休ませる方法。製造業などに向いているといます。
②交替制付与方式:班やグループ別で有給休暇を取得する方式。流通やサービス業といった、定休日を増やすことが難しい事業場に向いています。
※運用には就業規則や労使間での協定を結ぶ必要があります。「年次有給休暇取得促進特設サイト」にモデルが掲載されていますのでご参照ください。
しかし、一般的なオフィスで上記①、②の方式を運用することはハードルが高いと思います。
なかなか丸一日休むことができない職場ならば時間単位の有給休暇制度をつくることや、従業員の申請に委ねる場合であれば、取得率の高さを従業員の評価に反映させるなどして、“有給休暇を取りやすい職場づくり”を整備することで対応していくと良いでしょう。
有給休暇の消滅が目前となれば、業務の調整や人員の確保は一層困難になることも予想されます。
判例のような事態になる前に、日ごろから有給休暇の取得を計画的にすすめていくことが大切です。
あわせて読みたい関連記事
株式会社エムステージでは、産業医や保健師の紹介からメンタルヘルス領域まで、産業保健のあらゆるお悩みに対応するサービスを展開しています。人事労務課題にお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。

 ログイン
ログイン