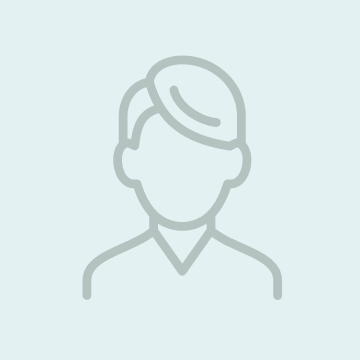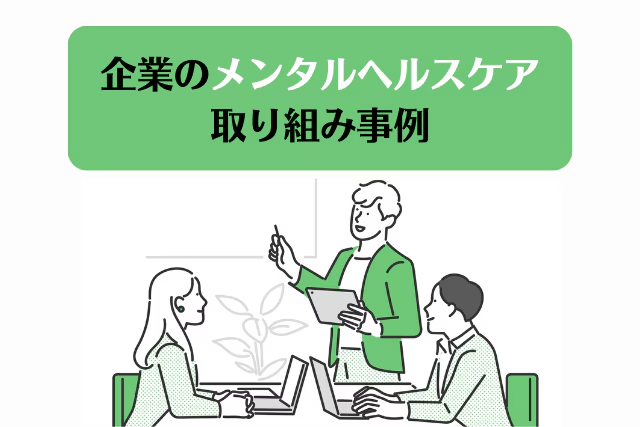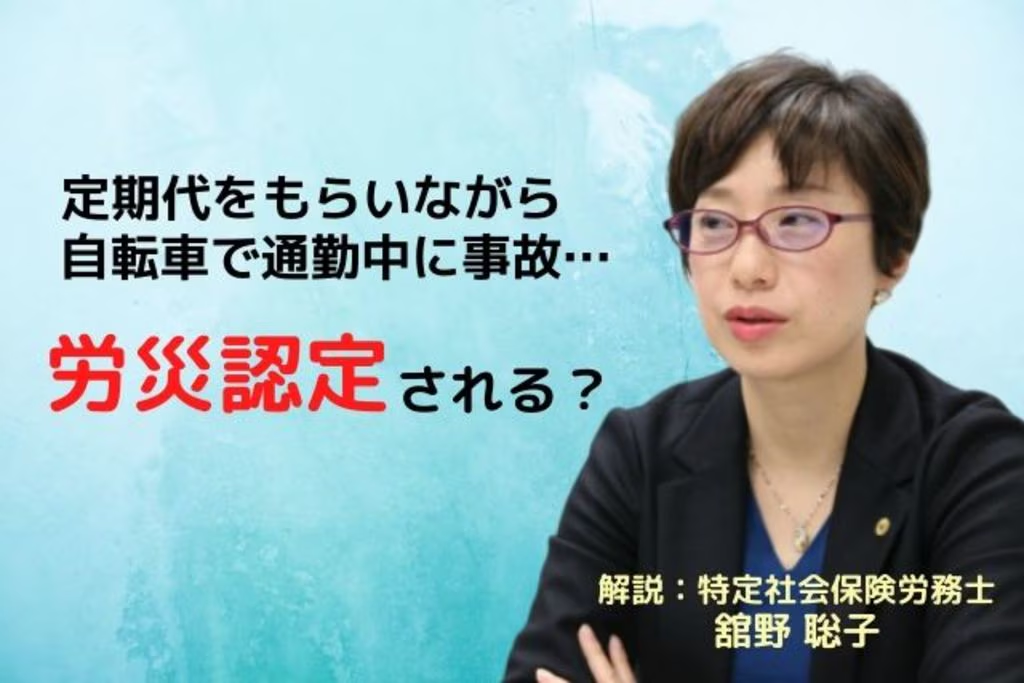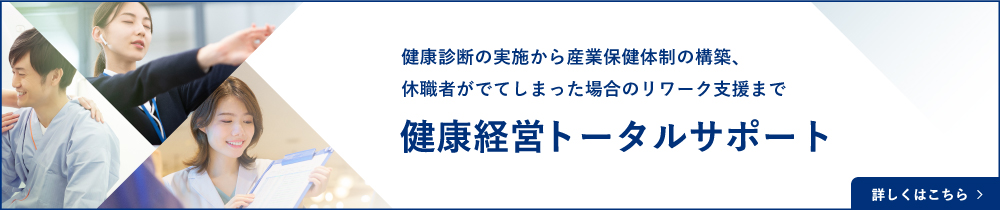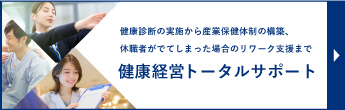<産業医コラム>働く人の靴を考える
(更新:)
長谷川 義真


みなさんの職場ではどんな靴を履いて仕事をしていますか? 革靴、スニーカー、安全靴、長靴またはスリッパという職場もあると思います。靴については個人が比較的自由に選ぶ職場が増えている一方で、その靴だと転ばないかなぁと心配になる人を職場に訪問した際に見かけます。
靴は足を守る重要な保護具の一つですが、歩行、体の重心に影響を与え、転倒のリスクにもなります。
転倒災害については令和3年度の災害発生件数は全国で33,672件と年々増加傾向です。特に50歳以上女性に多く、転倒の原因はつまずきが37.8%、滑りが31.8%の2つが全体の6割以上を占めます。対策は職場環境、作業環境の見直し、個人個人の身体機能改善、骨粗鬆症健診など長期的な計画必要になってきます。その中でまずは取り組みやすい対策として靴を正しく選び、履いていただくのはいかがでしょうか。
靴を考える上で大切なのは
・職場にあった正しく靴を選ぶことと
・消耗を確認することです。
【靴の選び方】
1 サイズに合った靴を選ぶ
靴が足合わないとスムーズに体重移動ができないため、ちょっとした踏み外しでも不安定になり転倒の恐れがあります。靴を共用する場合も十分なサイズ展開の準備をしましょう。
2 屈曲性のある靴を履く
靴の屈曲が悪いと足が疲れやすくなるだけでなく、摺足になりやすく、つまずく原因となります。
かがんだ際にしっかり屈曲するか、痛みがでないか確認しましょう。
3 踵がしっかり固定される靴を選ぶ
立位時踵が不安定な状態が続くと、下肢に疲労が溜まり、腰痛の原因となります。靴を履く際も踵にフィットするように合わせてください。
4 つま先部の高い靴を選ぶ
つま先部の高さ(トゥスプリング)が低いと、ちょっとした 段差(10㎝程度でも)につまずき易くなります。
5 重量バランス
つま先が重たい靴の場合、足関節が屈曲しにくくなり、つまずきの原因となります。特に高齢の労働者は注意が必要です。
6 床面に合わせた靴底を選ぶ
靴底の耐滑性は、職場の床の滑り易さの程度に応じたものと する必要があります。滑りにくい床に滑りにくい靴底では、 摩擦が強くなりすぎて歩行時につまずく場合があります。 JSAA規格の靴等には耐滑性を示すピクトがベロ裏に記されているので一度職場の靴を確認してみてください。記載がない靴はメーカーに問い合わせてみてください。

【靴の消耗を確認する】
適切な靴を選択していた場合でも、消耗した状態では十分な機能を発揮することはできません。
定期的に作業前に靴の裏の凹凸がすり減っていないか、かかと部が潰れていないか確認しましょう。
日頃から職場で転倒対策を意識付けすることから、転倒対策は始まります。ぜひ職場で話し合ってみてください。
参考
令和3年の労働災害発生状況を公表|厚生労働省
転倒予防・腰痛予防の取組 |厚生労働省
プロテクティブスニーカー
文章出典:株式会社イーウェル「健康コラム」より寄稿

 ログイン
ログイン