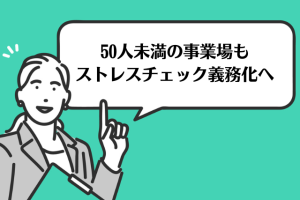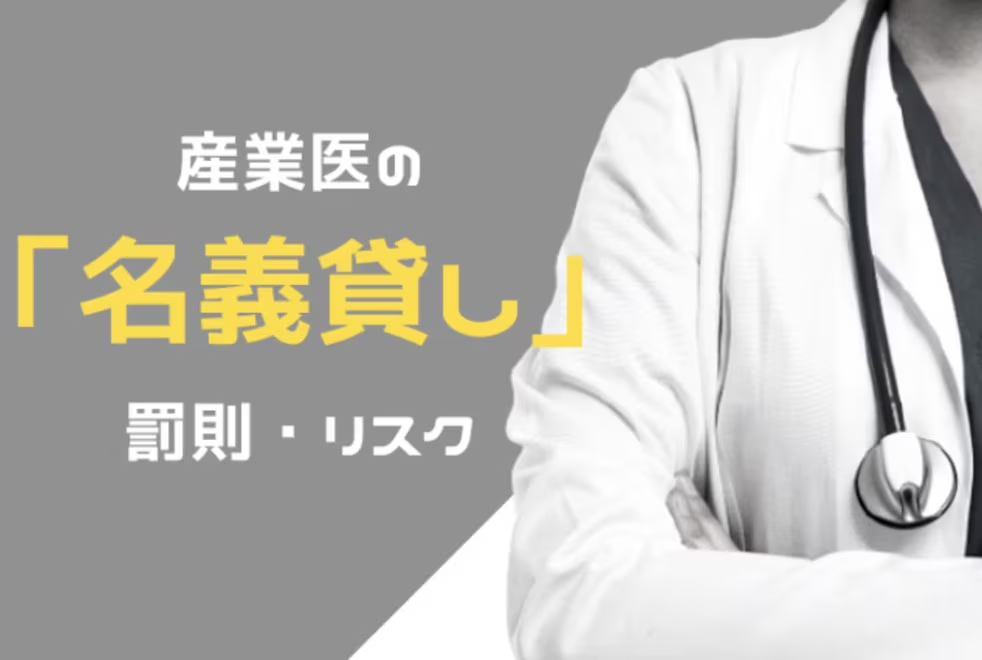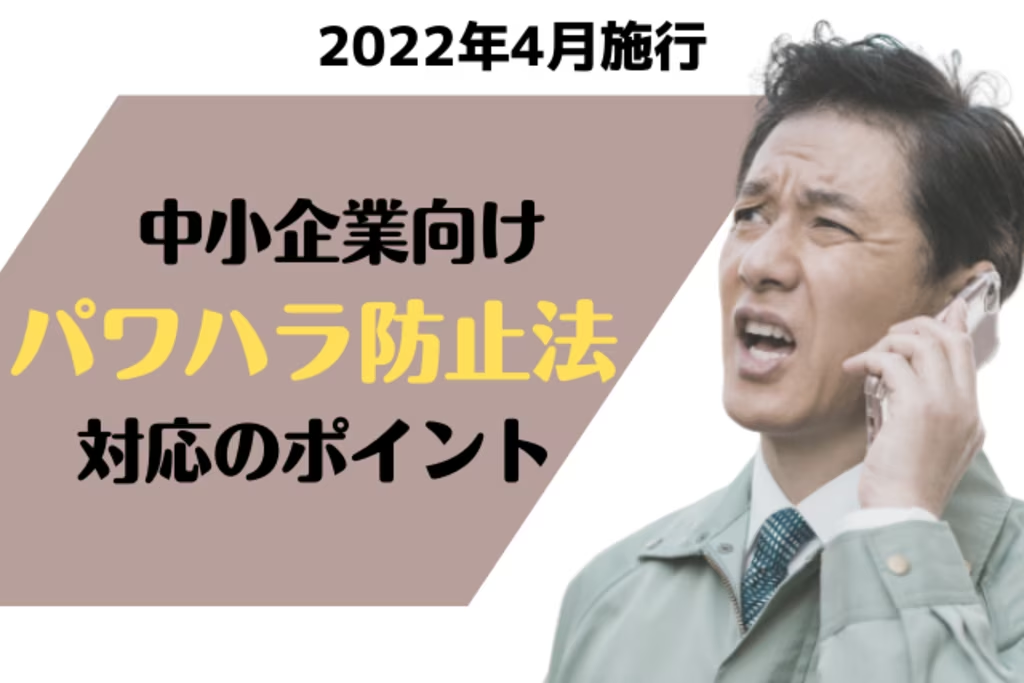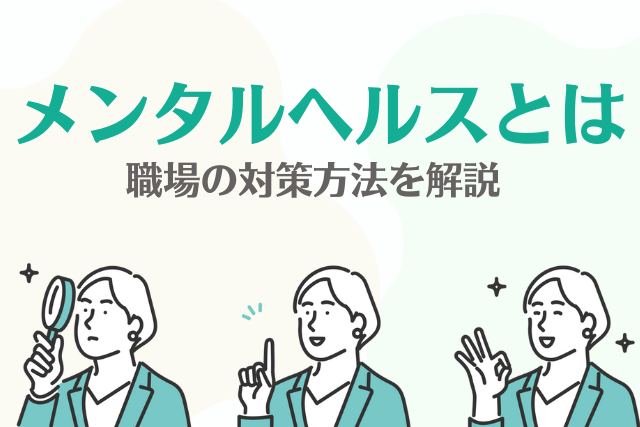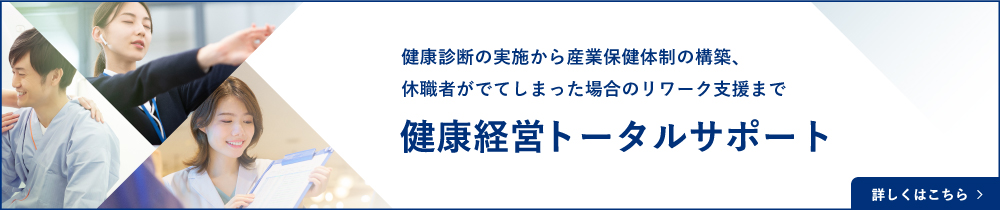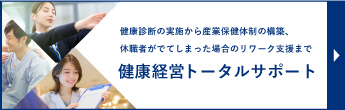【ストレスチェック】外部委託業者の選び方や委託するメリットを解説!
(更新:2025/02/19)
サンポナビ編集部
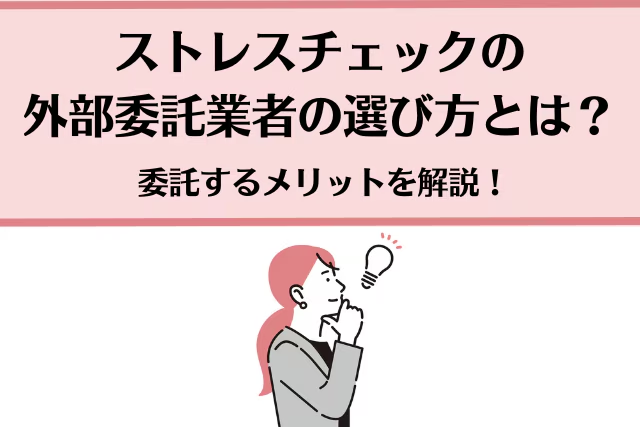
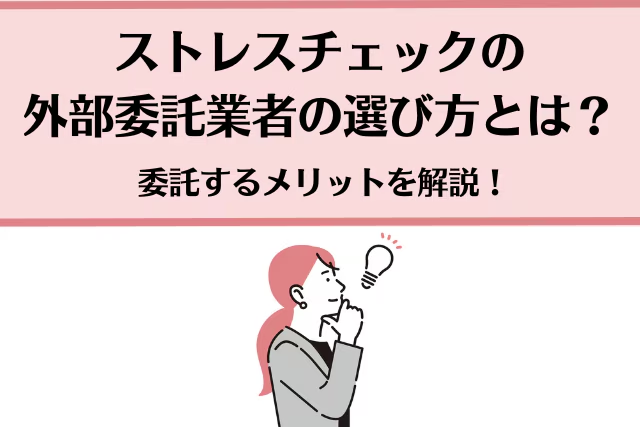
ストレスチェックの実施は、調査票の選定や採点、高ストレス者の判定などの業務が発生し、担当者の負担となるケースも少なくありません。
ストレスチェックは、外部委託することが可能です。専門業者に実施から結果の算出までを依頼することで、負担軽減につながります。しかし、「どの業者に委託すればいいかわからない」と、委託業者選びに悩む人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ストレスチェックの外部委託について、業者の選び方や委託するメリットを解説します。
\ストレスチェックの外部委託は『Co-Labo』/
目次 [非表示]
ストレスチェックの外部委託ができる範囲はどこまで?
厚生労働省のストレスチェック指針では以下のように規定されており、ストレスチェックの外部委託が認められています。
ストレスチェック又は面接指導は、事業場の状況を日頃から把握している当該事業場の産業医等が実施することが望ましいが、事業者は、必要に応じてストレスチェック又は面接指導の全部又は一部を外部機関に委託することも可能である。
出典「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)
それでは、外部委託ができる範囲に規定はあるのでしょうか。委託可能な業務範囲について詳しく解説します。
外部委託できる業務範囲
ストレスチェックの外部委託が可能な範囲として、以下の業務が挙げられます。
- 実施者、実施事務従事者の代行
- ストレスチェックの実施
- 受検結果の回収・集計評価
- 労働者への受検結果の通知
- 集団分析
- 相談窓口の設置
- 面接指導の申出の勧奨
- 面接指導の実施
ストレスチェックの実施から集計、集団分析までを委託可能です。また、相談窓口の設置や面接指導など、事後対応についても依頼できます。
外部委託できない業務範囲
ストレスチェックの外部委託ができない範囲は、以下の業務です。
- 自社のストレスチェック担当者の選任
- 衛生委員会での調査・審議(外部委託先と共同開催は可能)
- 社内規程の整備と労働者への告知
- 面接指導を行った医師からの意見聴取
- 高ストレス者への就業上の措置
- 職場環境改善策の実施
- 労働基準監督署への実施報告書の提出
担当者の選任や社内規程の整備など、ストレスチェック体制の整備は自社で決定する必要があるため、外部委託ができません。
また、医師からの意見聴取や就業上の措置などは、事業場の状況を加味しないと適切に行えないため、委託先と連携しながら、自社で実施する必要があります。
ストレスチェックを外部委託するメリット
ストレスチェックを外部委託するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 人事総務など社内の業務負担を軽減できる
- 職場環境改善のために取り組むべきことが明確になる
- 匿名性が高まり受検率の向上が期待できる
人事総務など社内の業務負担を軽減できる
外部委託により、ストレスチェックの実施事務従事者を代行できるため、人事・総務担当者の負担軽減につながります。
また、自社に産業医がいる場合でも、面接指導を行う体制が十分でないことがあるでしょう。例えば、産業医がメンタルヘルスが専門分野でないことを理由に面接指導を断られたり、対応時間のやりくりが難しかったりする場合です。
職場環境改善のために取り組むべきことが明確になる
集団分析を外部委託することで、職場環境改善のために必要な取組が明確化されます。自社でストレスチェックを実施した場合、集団分析まで手が回らず、効果的な改善施策につなげられていないケースがみられます。
集団分析も含めて外部委託することで、職場環境の改善点を発見でき、具体的な取組に生かせるでしょう。
匿名性が高まり受検率の向上が期待できる
社内でストレスチェックを実施する場合、プライバシーが守られるかを不安に感じ、従業員が受検をためらうケースがあります。また、評価に関わることへの懸念から、無難な回答しかしないなど、回答の信頼性が下がる恐れもあります。
外部委託により回答の匿名性が担保されるため、従業員が安心して回答でき、結果の信頼性も向上するでしょう。より正確な結果がわかるようになり、実効性の高いメンタルヘルス対策の実施が可能になります。
外部委託業者を選ぶポイント

厚生労働省の「ストレスチェック指針」では、ストレスチェックを外部委託する際には、以下の体制が整っているかの確認が推奨されています。
- ストレスチェック、面接指導を適切に実施できる体制
- 情報管理が適切に行われる体制
外部委託は認められているものの、委託しても問題がない業者を選ぶことが事業者に求められています。では、外部委託業者を選ぶときにはどのような点に気をつければよいのでしょうか。外部委託業者を選ぶポイントは次の5つです。
- ストレスチェック制度について正しく理解しているか
- 自社に適した実施方法を選択できるか
- 職場環境改善のサポートをしてくれるか
- 情報管理に関する第三者認証を受けているか
- 外部委託費用が適切か
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省)を編集して作成
1.ストレスチェック制度について正しく理解しているか
ストレスチェックの目的や守秘義務、結果通知の方法などの制度に関して、委託業者が十分に理解しているかを確認しましょう。具体的には、以下のポイントの理解や実施体制が整っているかを確認することが重要です。
- ストレスチェック結果の提供方法など、情報管理についての理解
- 実施者や実施事務従事者に対する研修・教育体制
- 産業医との連携体制
2.自社に適した実施方法を選択できるか
自社の従業員構成や業務形態に応じて実施方法を選択できることも重要なポイントです。受検が業務上の負担にならないよう、自社の従業員が受けやすい方法を選ぶことで、受検数や信頼性の確保につながります。具体的には、以下のようなポイントをチェックしましょう。
- Web受検の可否
- 外国人労働者向けの多言語対応
- 設問項目数
- 独自尺度の有無
外部委託業者によっては、厚生労働省推奨の職業性ストレス簡易調査票だけでなく、独自の尺度を提供しているケースもあります。独自尺度の場合、以下の3つの内容を含む質問票であることが求められます。
- ストレス要因(職場における当該労働者の心理的な負担の原因)
- 心身のストレス反応(当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状)
- 周囲のサポート(職場における他の労働者による当該労働者への支援)
「ストレスチェック制度に関する法令」(厚生労働省)を編集して作成
3.職場環境改善のサポートをしてくれるか
職場環境改善に向けて、集団分析の実施と活用までのサポート体制があるかを確認します。部署ごとの集計や分析結果をわかりやすく示し、自社の産業医と連携しながら具体的な職場改善提案ができるかが重要です。
また、分析を行う対象集団の選定が適切かも確認しておくべきポイントです。個人が特定される恐れがあることから、10人未満の集団に対する分析は推奨されていません。対象とする集団の単位について、プライバシーに配慮した提案ができる委託業者を選びましょう。
4.情報管理に関する第三者認証を受けているか
ストレスチェック結果などの個人情報の管理は法令上の要件であり、特に重視すべきポイントです。委託先の情報管理体制をチェックする際には、第三者認証の取得状況を確認しましょう。代表的な第三者認証として、個人情報の取扱いに関するプライバシーマークや、情報セキュリティ管理に関するISMSがあります。
また、ストレスチェックの実務に関して、以下の点が守られているかを確認しておきましょう。
- 調査票の記入から結果の保存までを第三者が確認できない方法で実施しているか
- パスワード管理や不正アクセス防止などのセキュリティ対策は万全か
- 保存データの暗号化がなされているか
- 個人情報の取扱いに関する社内規程が整備されているか
- 情報漏えい時の対応がマニュアル化されているか
5.外部委託費用が適切か
費用面では、基本料金に含まれるサービス範囲と、追加料金が発生するオプションを区別して把握しましょう。特に、データ保管料や面接指導の勧奨などの別途料金の発生、集団分析の上限設定があるかの事前確認が大切です。
費用の安さだけでなく、自社に必要なサービスを受けられるよう、提供範囲と料金体系をチェックしておきましょう。
外部委託する場合の注意点
ストレスチェックの結果は、労働者の同意がない場合、実施者と実施事務従事者以外には開示できません。そのため、外部委託すると、結果を確認するために労働者の同意が必要となり、円滑に活用しにくくなります。
ストレスチェック制度の本来の目的は、労働者自身のストレスへの気づきを促し、働きやすい職場づくりを進めることです。外部委託する場合でも、委託先と自社の産業保健スタッフが連携し、ストレスチェック実施後の措置や対策が効果的に行える体制づくりに努めましょう。
自社に産業医がいる場合は「共同実施者に」
厚生労働省では、外部委託時の連携体制構築のため、自社の産業医を共同実施者としてストレスチェックに関与することを推奨しています。共同実施者とは、自社の産業医と委託業者の医師が共同でストレスチェックを実施する場合など、複数名いる場合の実施者を指します。
自社の産業医が共同実施者になるためには、ストレスチェック実施に関して、最低でも以下のような関与が必要です。
- 調査票や高ストレス者選定基準を決定する際の意見
- ストレスチェック結果にもとづく面接指導の要否の確認
上記を共同実施者として自社の産業医が行うことで、より実効性のある職場改善施策につなげられるでしょう。
「ストレスチェック制度関係 Q&A」(厚生労働省)を編集して作成
50人未満の事業所もストレスチェックの義務対象へ

令和6年10月の厚生労働省の検討会において、50人未満の事業場でもストレスチェックを義務化する方向性が示されました。50人未満の事業場におけるストレスチェック実施率の伸び悩みや、メンタルヘルス不調者の増加傾向を背景に、義務範囲が拡大される見込みです。
しかし、50人未満の事業場では産業医の選任義務がなく、ストレスチェックや面接指導を行う体制が整っていない企業も多いでしょう。適切な施策のためのリソースやコストを割くことが課題となりやすいため、外部委託がおすすめといえます。
「第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案」(厚生労働省)を編集して作成
あわせて読みたい関連記事
ストレスチェックの外部委託なら「Co-Labo」
株式会社エムステージでは、官公庁や大手・中小企業まで幅広くご活用いただいているストレスチェックサービス「Co-Labo」を提供しています。
法定のストレスチェック項目にはない独自設問や、虚偽申告傾向回答者を除外した精密な集団分析で、自社の課題を正確に抽出します。また、実施の中で不明点があれば、専門スタッフによる運用サポートなど、手厚いサービスが受けられ、負担軽減につながります。
さらに、産業医紹介や専門職のオンラインシェアリングサービスなど、メンタルヘルス対策に必要なサービスをワンストップで提供。ストレスチェック実施後の面接指導や職場環境改善など、事後対応も安心してお任せいただけます。ぜひお気軽にお問合せください。

 ログイン
ログイン